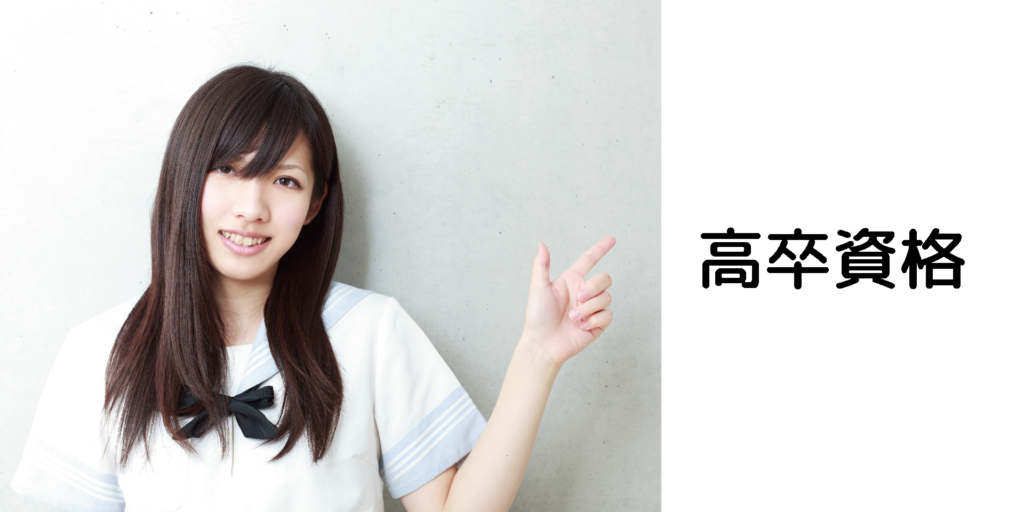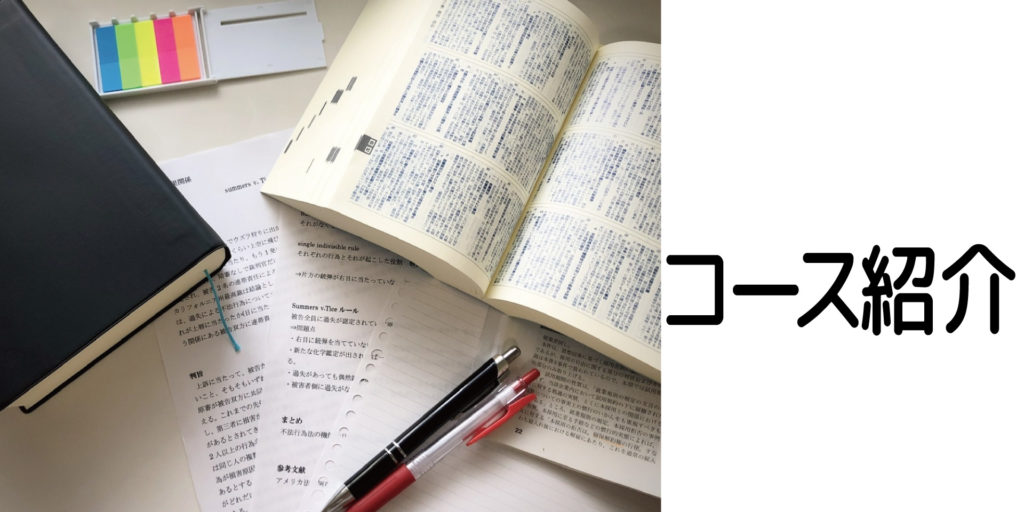問いを立てられる人になろう。
 高校とは何のためにあるのだろう。有名な大学に行くため?その先、大企業に行くため?それもあるかもしれない。でも、それだけじゃない。少なくともここ松陰高等学校では与えられた問いに応えられる。それより私たちが大切に考えるのは「自ら問いを立てること」。何のためなのか?誰のためなのか?常にそう考えることを通じて、物事の本質をとらえる力をはぐくむ。それは「自分とは何者で、どこに向かうのか」という一番大切なっことを自らに問い、可能性を模索することへとつながっていく。既存のシステムに問いを立て、よりよい社会をつくる、その一人になっていく。生徒たちもちろん、この学校で働く大人たちも。人生に回答用紙は無い。そこにあるのは、白紙だけ。さあ、共に問いをたてよう。
高校とは何のためにあるのだろう。有名な大学に行くため?その先、大企業に行くため?それもあるかもしれない。でも、それだけじゃない。少なくともここ松陰高等学校では与えられた問いに応えられる。それより私たちが大切に考えるのは「自ら問いを立てること」。何のためなのか?誰のためなのか?常にそう考えることを通じて、物事の本質をとらえる力をはぐくむ。それは「自分とは何者で、どこに向かうのか」という一番大切なっことを自らに問い、可能性を模索することへとつながっていく。既存のシステムに問いを立て、よりよい社会をつくる、その一人になっていく。生徒たちもちろん、この学校で働く大人たちも。人生に回答用紙は無い。そこにあるのは、白紙だけ。さあ、共に問いをたてよう。
自立性の確立
自分で考え「問いを立て」知・徳・体に渡る「生きる力」手に入れる
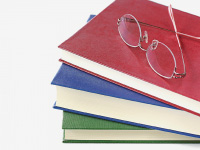 戦後の日本は、工業で立国しました。その時代に必要な人材は、「言われたことを言われた通りにできる人」。だから学校教育も、「与えられた問いに答えられる子ども」を優秀とし、均質にそういう人材を育てるシステムでした。これからは、誰かに何かを指示される時代ではありません。混沌とする現代社会に必要なのは、問いを解けることではなく、「問いを立てられる」こと。
戦後の日本は、工業で立国しました。その時代に必要な人材は、「言われたことを言われた通りにできる人」。だから学校教育も、「与えられた問いに答えられる子ども」を優秀とし、均質にそういう人材を育てるシステムでした。これからは、誰かに何かを指示される時代ではありません。混沌とする現代社会に必要なのは、問いを解けることではなく、「問いを立てられる」こと。
その中で、自分とは何者で、何がしたいのかを自らに問い、社会とどうつながるかを考える。知・徳・体に渡る「生きる力」を手にいれる。松陰高等学校での3年間は、そのためにあります。
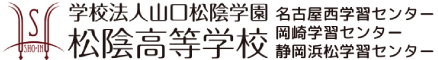

 松陰高等学校の本校は、山口県。「19世紀末の世界史の奇跡」といわれる日本近代化の礎を築いた山口。ここには、「一方的な教えでなく、対話によって可能性を引き出す」教育が根ざしています。その教育環境の下、数多くの傑出した人材を育てた一人が、吉田松陰先生です。「学ぶことを願うならば、いつでもどこでも学ぶことができる」。先生がいつも実践されていたことは、まさに「通信制」の先駆けです。その名を冠す学校として。
松陰高等学校の本校は、山口県。「19世紀末の世界史の奇跡」といわれる日本近代化の礎を築いた山口。ここには、「一方的な教えでなく、対話によって可能性を引き出す」教育が根ざしています。その教育環境の下、数多くの傑出した人材を育てた一人が、吉田松陰先生です。「学ぶことを願うならば、いつでもどこでも学ぶことができる」。先生がいつも実践されていたことは、まさに「通信制」の先駆けです。その名を冠す学校として。 松陰高等学校は、「みんなのための高校」ではなく、「一人ひとりのための高校」です。クラスや授業は、少人数制。「均質な教育」という考えは、わたしたちにとって重要ではありません。それよりも、一人ひとりの、「どう社会とつながるか」
松陰高等学校は、「みんなのための高校」ではなく、「一人ひとりのための高校」です。クラスや授業は、少人数制。「均質な教育」という考えは、わたしたちにとって重要ではありません。それよりも、一人ひとりの、「どう社会とつながるか」


 歴史的に見て山口県は日本の近代化を導いた寺子屋教育の成果を上げた地である。松陰高校はこうした教育の精神を学び、画一的な授業形態とは異なる少人数で生徒の「個」に応じた学習スタイルを基本に、生徒の個性や可能性を引き出す教育を目指します。比較的自由に時間を使えるという通信制高校のメリットを生かしながら、生徒たちが学問の面白さを実感し、自信を持ち、進路の実現を果たせるサポートを続けます。
歴史的に見て山口県は日本の近代化を導いた寺子屋教育の成果を上げた地である。松陰高校はこうした教育の精神を学び、画一的な授業形態とは異なる少人数で生徒の「個」に応じた学習スタイルを基本に、生徒の個性や可能性を引き出す教育を目指します。比較的自由に時間を使えるという通信制高校のメリットを生かしながら、生徒たちが学問の面白さを実感し、自信を持ち、進路の実現を果たせるサポートを続けます。